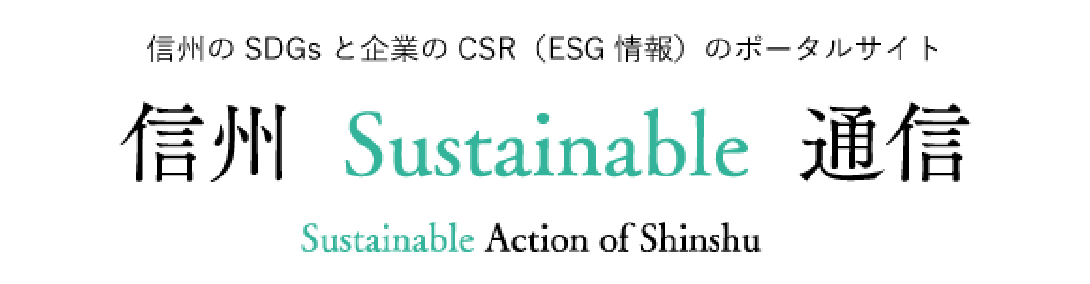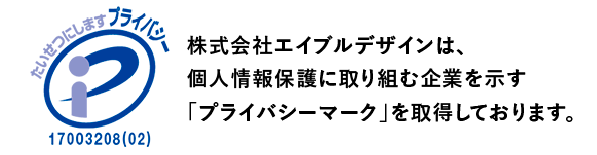「気候変動の適応」と「ありのままの自然の力」
松本支社ディレクターのWです。
過去最高の暑さが、人間を含めた生き物にさまざまな影響を与えている。
気候変動のためにできることは、気候変動の「緩和」のために温室効果ガスの排出を削減する取り組み。そして、気候変動に「適応」し、その被害を回避・軽減させる取り組みだ。
農作物の栽培において、気候変動の影響を最小限にする「適応」とはなんだろう。お金をかけず誰にでもできる「適応」は、ありのままの自然の力を借りることだろう。
食の革命家アリス・ウォータースが自身の集大成著書「スローライフ宣言」でこんなことを提言している。
「持続可能な仕組みは、すでに自然の中にある。自然の循環の中に人間が入っていくことによって、持続可能性が保たれる」
気候変動に対抗するため、私が営んでいるような小規模の畑では、土壌生態系の保全・再生がとても重要だと実感している。私の畑で長年実践してきた最善策は、耕さず(不耕起)、常に表土が裸にならないよう植物を生やし、必要な場合は草を刈りその有機物(草)で表土を覆うことで、土壌中に棲む土壌生物が棲みやすい環境を提供してあげることだ。
土壌生物(小型動物・微生物)が元気に活動することで、5億年前から育まれてきた自然の生態系がもつ栄養循環のしくみ、そして水分を土中に保持するしくみが機能する。そうなれば、当然個体差はあるが、水不足に対抗するために団粒と土壌微生物を包み込む根圏を育み、酷暑の夏でも植物はへこたれず元気に生長してくれる。
土壌中の細菌、真菌類、原生動物、藻類、ダニ、線虫、ミミズ、アリ、甲虫の幼虫、甲虫、昆虫、モグラ、ハタネズミなどは、お互いを食べ、繁殖し、廃棄物を代謝させ、ミネラルを可溶性にし、地上の植物が栄養を吸収できるようにしてくれる。土壌は生物多様性を生み出す賑やかなコミュニティである。
特に、ミミズは小さな生き物だが、毎日ほぼ体重と同じ量の土と落ち葉を食べ、せっせと糞を排出している。そのほとんどが耐水性団粒として土壌に集積する。不耕起・草地の地面は、実に3割~4割が、窒素やリンなどの栄養がたっぷり含まれるミミズの糞起源であると推測できるようだ。(金子信博著「ミミズの農業改革」より)
だから、春から秋にかけては、畑にミミズが棲みやすい環境をつくることが農作業の中心になる。ミミズの糞が多い土壌は作物の育成に最高の環境となるからだ。