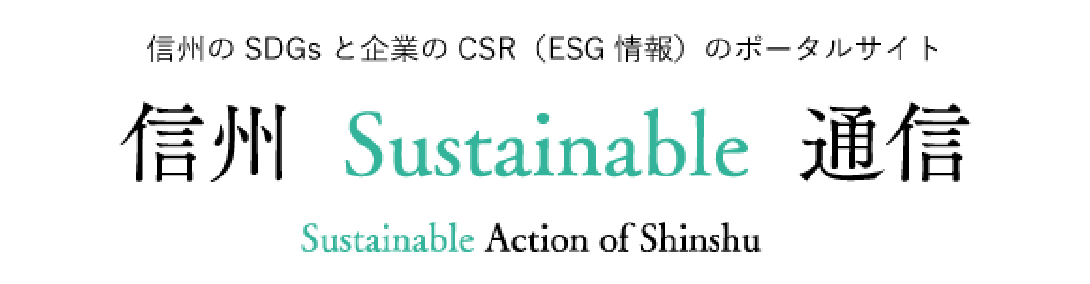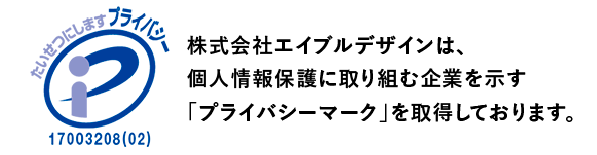ふだん歩く道に、江戸の名残を見つけて
こんにちは。長野本社のK.N.です。
私の家の近所には、江戸時代に整備された脇街道(五街道以外の主要道路)の一つ、「北国街道」が通っています。
この街道は中山道の追分宿から分かれ、信州を北上して善光寺を経由し、日本海側の直江津へと通じていました。
どこまでを結んでいたのか、またその呼び方については、時代や地域によって諸説があるようです。
かつては、佐渡の金銀の輸送や大名の参勤交代の往来でにぎわいを見せた歴史ある道ですが、私にとっては日常生活に欠かせない生活道路の一つ。
普段はその歴史を意識することもなく通っていました。
ところがある日、近所のスーパーに歩いて出かけ、信号のない三叉路で車が通り過ぎるのを待っていたとき、ふと案内板と石柱が目に入りました。
そこには「飯山街道分岐道標」とあり、北国街道と飯山街道の分岐点であることを示していました。
石柱には、
「右 いい山 なかの 志ふゆ くさつ 道(飯山・中野・渋湯・草津方面)」
「左 北國往還(北国往還)」
と刻まれています。
案内板によると、「当時、善光寺参り等の後、中野、飯山、渋温泉、草津温泉方面へ用件や湯治で行く人々のための道標だったと思われる。......」と説明されていました。
往時、「北国街道善光寺参り」の基点となっていたこの場所は、現在では車の往来が激しいものの、生活に欠かせない便利な道路として今も残っています。
その歴史と現代生活とのギャップに面白さを感じ、この街道に改めて興味が湧いてきました。
この近辺にはかつて、善光寺宿(1里)と牟礼宿(2里半)の間に「新町宿」がありました。現在は住宅街といった雰囲気ですが、当時を思わせる名残もちらほら見られます。
主要な道筋だけでなく、街道の裏手にある細い道にも歴史を感じさせる場所があります。そこにも案内板が立っており、こう記されています。
「街道裏道:北国街道は、加賀藩や高田藩などの殿様が参勤交代で通るときは、住民の通行が出来なかったため、住民は生活道として、裏道を使って行き来をしたと言われている。......」
なるほど。昔も今も変わらず、住民たちにとっては安全に行き来するための裏道が必要だったのでしょう。
全国の街道や宿場にも、このような裏道があったのだと思うと、人々の暮らしの目的に応じて道が形づくられてきたことを改めて実感しました。
街道筋をゆっくり歩いてみると、歴史や地域の空気を味わいながら、時代の移り変わりに思いを馳せることができます。
こうした楽しみ方も良いものですね。
またどこかを歩いてみたい― そんな気持ちになった今日この頃です。